【業競合が近くに?】“あえて競合の隣”が成功する理由とは📊🔥 立地で勝つ店の戦略
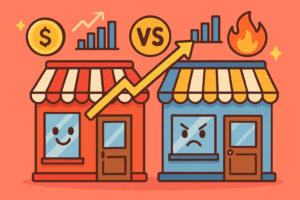
「隣に同じ業種の店がある…競合か〜」と思ったあなた、ちょっと待ってください。実は“あえて競合の隣”を選ぶオーナーさんが増えてるんです。その理由と、「どうやってその競合の近さを逆手に取るか」の戦略を紐解いてみましょう📍
⚙️ 競合が近い場所を選ぶメリット
- 集客力の引き上げ=“人が来る場所”になる力
複数の同業店が集まると、その通りがその業種で“目的地化”します。例えばラーメン店が複数あるエリア=ラーメンを食べたい人が集まるところ。お客さんが「ここに行けばラーメンが食べられる」と思って来るので、流入人口が増えやすい。
- 比較されることで質が磨かれる+差別化できる機会
近くに似たお店があると、お客さんは“価格・味・サービス・雰囲気”を比べます。これは自分たちの強みを際立たせるチャンス。たとえばメニューでこだわる部分を明確にしたり、接客スタイルで個性を出したりすることで、「あそこの店はこの点がいい」と言ってもらえることが増えます。
- 集積の経済・相乗効果で業務が効率化することも
人気エリアだと、看板設置や集客広告・宣伝費が共有されるようなムードが出たりすることがあるし、お客さんの動線が定まっているため“通行人がついでに入る確率”も上がります。「あそこに飲食店がたくさんある」ということでまず目につきやすい。
- 競合店があるから、立地条件や動線などをしっかり見られる
近くに競合がいれば、「あの店はどこが強みかな?どの時間帯が混みそうかな?」と観察できるので、自分の出店場所・時間帯・プロモーション内容などの戦略をより緻密に作れます。
⚠️ もちろんデメリットもある!けど対策あり
| デメリット | 対策ポイント |
|---|---|
| 価格競争になる可能性 | 競合価格を調べて、自店の強み(品質・雰囲気・サービス)で差異を打ち出す。固定客を作る工夫を。 |
| 流入客が分散してしまう | メニューやサービスで個性を際立たせる、「ここでしか味わえない体験」を提供する。 |
| 初期賃料・物件コストが高くなりがち | コスト対効果を見極めて、家賃交渉や条件(造作・契約期間等)で折り合いをつける。 |
🔍 競合が隣にあって成功するテナントの選び方
- 強みの差別化を明確にする
味・メニュー構成・接客・雰囲気など、自分の売りを把握し、それを競合と比較してどこが違うのか言語化すること。
- ターゲット層のズレを探る
競合が“若者向け”“カジュアル系”なら、自分は“女性寄り”“深夜対応”“ゆったり系”など、微妙な顧客層のズレを狙う。
- 営業時間・サービス時間で工夫をする
競合が昼間だけ営業なら夜間営業に特化するなど、時間帯で差をつけると混雑を避けつつ稼ぎやすくなる。
- 立地・通行量・視認性を重視
続けて人通りが多く、入口が目立つ物件なら、通りすがり客を取り込む力がアップ。通りやすいビル入り口・看板・ネオンなども重要。
- 価格戦略・販促戦略を練る
初期プロモーション・SNS・イベントなどで「隣の人気店があるからこのエリア」という注目を集め、それを味方につける宣伝をする。
🎯 まとめ:競合を“隣人”にするメリットを活かそう!
競合が近くにあるのを“リスク”と捉えるか、“チャンス”と見るかはあなたの戦略次第。隣に競合があることでエリアとしての魅力=「そこにいけば欲しいものが揃っている」という集客の土壌ができるのです。差別化をきちんと設計し、磨きをかけて、自分の強みを最大限に活かすことで、競合の隣でも成功できるテナントを選ぶことが可能です。

すすきの、札幌近郊での仲介・売買・管理は、 ぜひHomeAgentへ
すすきのテナント仲介、業界実績No.1! お店を出すときはぜひ弊社にお任せください! 地域密着型、というよりお客様密着型のお店! HomeAgentが理想のテナントをお探しします。